通勤電車内で本が読みたくなった。
たまにこんなことがあるので、いくつかKindleに本をダウンロードしてある。多くは青空文庫。
最初、自動的に開いたのは「ローマ帝国衰亡史」(だったかな?)。数ページ読んで、なんか今の気分とは違うなと思った。
それを閉じると、ライブラリには萩原朔太郎の「月に吠える」が出てきた。青空文庫でダウンロードしたものの、あまり読んでいなかったやつだ。
僕のkindleライブラリーにはこういうのがたくさんある。
詩を読むなんてすごく久しぶりだ。いくつか読んだ。竹についての詩だった。・・・よくわからん。
その後5、6編読んで閉じた。どうやって楽しんだらいいのか・・・。こういったものを味わえる感性が僕には無いんだろう。
ネットで「詩 楽しみ方」と検索してみた。理由はわからないけれど、何かの楽しみ方を検索するって行為には屈辱的な感じがする。そう思いながら検索結果をスクロールしていくと、詩人・谷川俊太郎さんの記事が出てきた。
その中で詩を楽しみたい子供たちへのメッセージとしてこう書かれていた。
「言葉の意味は辞書を引けばわかる。でも、けんかしたり、人を好きになったりした時に出てくる言葉はきっと、辞書では定義できない。そうした言葉の広がりを感じ取れる感性を大事にしてください」(朝日小学生新聞「谷川俊太郎さんに聞く 詩の楽しみ方」より)
ふむ。確かに言葉で言い表せない感情というのはなんとなくわかるような。最近、僕が日常生活で触れる言葉はどれも何かを明示していると思う。
仕事においてはそれこそ重要だと思っているし、何事においても、誤解無きよう、正しく伝わるようと省略し、簡潔にしている。言葉の広がりなんて皆無だろう。
でも、詩を楽しむときはそれを大事にせよとのこと。なるほど。今後は少し意識してみよう。
<おわり>

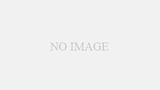
コメント